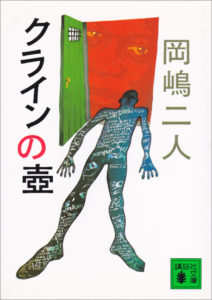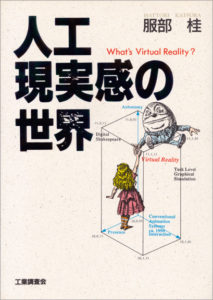『99%の誘拐』(1988年)
主人公の生駒慎吾は、子供の頃誘拐された過去があった。慎吾を助けるために支払った5千万円が原因で、父親が経営していた会社は大企業に吸収合併される。20年後、大手企業リカード社のプログラマーとなった慎吾は、当時の犯行グループを相手に復讐の誘拐事件を仕掛ける…
人質である少年をおびき寄せて監禁する手順から、家族との電話対応、身代金受け渡し方法の伝達まで、すべてをコンピュータによる合成音声とパソコンによる指示で行い、犯人は一度も姿を見せない誘拐事件。それをSFではなく、実際に販売されていた電子機器だけでやりきった。当時はまさに衝撃的な作品だった。
もちろん技術は古びる。何しろまだWindows3.1すら発売されていない時代の作品である。しかしこの小説はそれから17年後、2005年の「この文庫本がすごい!」で第1位に選ばれている。すでに携帯電話が普及し、インターネットが当たり前になった頃に、黒い画面に緑のコマンドを叩き込んでいたMS-DOS時代の作品が再評価されたのだ。
これこそ、岡嶋二人の「プロット作りのうまさ」の証明だと思っている。
まず、この物語を謎解きの形式ではなく、犯人側からの倒叙形式で描いたこと。
まだパソコンについての知識が世間に浸透していなかった時代。謎解きの形式でこのトリックを披露すれば、多くの読者が騙されたかもしれない。しかし作者はそうしなかった。
主人公はパソコン(実は自分)からの指示で、自身を身代金の運搬役に指名し、事件に巻き込まれた一般人を演じてみせる。復讐という同情のできる動機を用意することで、読者を犯人側に肩入れさせておき、コンピュータを利用した犯罪など果たして成功するのか? というサスペンスで物語を引っ張る。ここがうまい。作品の前半、誘拐計画のすべての準備を終え、空港のトイレを出る生駒慎吾の姿には、これから舞台に立つ役者が堂々と楽屋を出るときのような高揚感がある。
かくいう私も、この生駒慎吾に憧れて、当時数十万円したパソコン機器一式を買い揃えた一人。その後、私の興味はMACに移り、独学でMACの勉強を始め、現在の職業にたどり着く。まだ量販店にはMACを置いておらず、価格もバラつきがあり、本体と周辺機器を別の店で買うのは当たり前。秋葉原の雑居ビルにあった輸入専門のショップを転々として、いちばん安い店を探した。
ジャンク屋とか、パソコン通信とか、そんなものに触れること自体に何となくアングラ感が漂っていた時代だった。98年のファンタジーノベル大賞を受賞した『青猫の街』(涼元悠一)という小説があるが、黎明期のネット界隈の怪しげな雰囲気がよく表現されていた気がする。
こんな思い入れの強い作品だから、『おかしな二人』(岡嶋二人を解散した後、井上泉氏によって書かれた岡嶋二人の自伝的エッセイ)を読んだときには、話が『99%の誘拐』にたどり着くのが怖かった。
ここに書かれているエピソードを読むと、読者には人気の作品でも、作者にとっては不本意な仕事だったこともあるのが分かる。例を上げれば「遅れて来た年賀状」(短編集『記録された殺人』『ダブル・プロット』に収録)。日常の謎のちょっといい作品として、岡嶋二人の短編の中では人気が高い作品だったと思うのだが、これが納得のいかない仕事として紹介されていたことが、少し寂しかった。
しかし物語は進んでいく。
87年『そして扉が閉ざされた』、『眠れぬ夜の殺人』。
そして翌88年、いよいよ『99%の誘拐』の章。
そこには、こう書かれてあった。
実際、それは僕たちの最後の総力戦だった。(『おかしな二人』より)
気がつけば、涙がボロボロと溢れていた。
私が大好きだった『99%の誘拐』は、作者にとっても自信作だった。
「総力戦」と呼んでもらえる作品だった……と。
『クラインの壺』(1989年)
KLEIN2と呼ばれるVRゲームのモニタとなった大学生に、次々と不可解な出来事が起こるストーリー。VRゲームを題材にした日本の小説の中では、最初期の作品だと思う。
当時はVR(Virtual Reality)のほかに、AR(Artificial Reality)という言葉もあり、どちらの呼び方が主流になるか、まだ分からない時期だった気がする。
私の手元に1991年発行の『人工現実感の世界』(服部桂)という本がある。
この本によると、VR技術の一般デビューは、1989年6月7日にサンフランシスコで行われたTexpo’89というイベントだったという。そこでVPL Research社が開発したRB2(Reality Built for 2)というVRシステムのデモが行われた。データグローブ+ヘッドセットの組み合わせで、現在の私たちから見ても不自然はない仕様である。
いっぽう、岡嶋二人の『クラインの壺』は1989年10月に新潮社から刊行されている。
岡嶋二人は、このイベントを知っていたのだろうか? 「KLEIN2」と「RB2」どことなく共通点があり、私は知っていた気がするが、ここから着想を得たとするといくらなんでも早すぎる。
そもそも『おかしな二人』に、こんな記述がある。
この当時〈バーチャルリアリティ〉とか〈仮想現実〉といった言葉は、一般に知られていなかった。実は、僕も知らなかった。だから、タイトルが決まるまで、この作品は僕たちの間で〈カプセル〉と呼ばれていた。(『おかしな二人』より)
ここでいう「この当時」とは1988年のことである。さらに別のページにはこの原案のことを「十四年前から僕の頭に巣食っていた魅力的な素材」と記述しており、かなり昔からのアイデアであったことがわかる。
実際にどのような技術を投入するのかの説明がない〈仮想現実〉ものならば、60年代にフィリップ・K・ディックの『追憶売ります』等が書かれているわけで、本来の案はいまよりもっとSF寄りのものだったのかもしれない。
単純に仮想現実ものというと、ちょうど同じころに竹本健治の『腐食の惑星』がある。調べてみるとこちらは1986年10月の刊行で、こちらのほうが少し早い。これは意外だった。なぜか日本の作家は仮想現実ものに対する取り組みが早い。『ドグラ・マグラ』の国の人だからだろうか。
『クラインの壺』を現在の若者が読むと「発表された当時は、遠い未来のおとぎ話だったのかもしれない」という感想になるらしいが、実はそうではない。現在のVR装置として思いつくのは、ヘッドセット+コントローラーだが、前述したようにこれらは当時でも存在していた。つまり、レコードからCD、CDからデータのような技術の革新は起こっていない。CDの音質が上がったようなものだろうか。作中に登場するKLEIN2のようなVR装置は今でも開発されておらず、その意味では2022年の現在でも、これは遠い未来のおとぎ話といえる。
私の記憶が正しければ、この作品が刊行されたとき、すでに岡嶋二人の解散は発表されていたと思う。そのせいだろうか。作品の面白さや内容ははっきり覚えているけれど、なぜかこれを読んだ当時のエピソードがあまり思い出せない。
読み終わると同時に、寂しさを感じたことがその理由だろうか。
当たり前のことだが、岡嶋二人の新作が発表されることはもう二度とない。
なので最後にこれを伝えたい。
同時代に素晴らしい作家がいて、私はとても楽しかった。
面白い本をたくさん、残してくれてありがとう。
そしてあらためて、徳山諄一さんのご冥福をお祈りいたします。