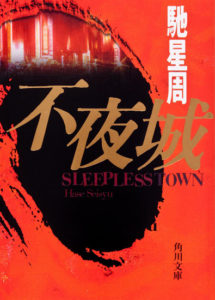暑い… ですね。
昔の日本の夏って、こうじゃなかったよね。午前中の涼しいうちにラジオ体操とか、日が傾いてきたら打ち水をして夕涼みとか、一日のあいだにメリハリがあったのが普通。それがここ数日は、夜中の12時に30℃超え、最低気温が28℃なんて日常茶飯事。もはやコロナがなくても休日に外出などしたくない… いや、できない!
そんなわけで、今回はもうやけくそ企画。
「真夏のミステリ〜ベストテン」を選出してみた。
せめて小説の中だけでも、かつてののどかな夏を堪能してみたいと思います。
…ま、そうじゃないのも入ってるんだけど(笑)。
1.『ソロモンの偽証』宮部みゆき(平成24=2012年)
終戦記念日は、毎年必ず、よく晴れる。
それは、昭和二十年八月十五日の快晴があまりに印象的だったことからくる思い込みで、実際にはそんなことはないのかもしれない。(本文より)
まずは平成20年代の作品から。
私にとって、宮部みゆきや恩田陸は夏休みイメージの強い作家です。
なのに恩田陸の場合、実際に探してみると、夏が舞台のものが意外に少なかった。『月の裏側』は梅雨時だし、『黒と茶の幻想』は夏の屋久島のイメージだけど、実は秋。
いっぽう宮部みゆきには、この『ソロモンの偽証』がありました。事件発生はクリスマス・イブの夜だが、学校内裁判の開廷は8月15日。閉廷は8月20日。
平成24(2012)年と比較的最近の作品にも関わらず、最近のようなギトギトした暑さの描写はないですね。不快指数でいうと60%ぐらいか。
[猛暑度=60%]
2.『夜市』恒川光太郎(平成17=2005年)
お次は平成10年代の作品。
屋台、縁日という夏っぽいものを想起させる作品ということで選びましたが、読み返してみると季節は夏ではなく、秋でした(笑)。
実は、これに同時収録されている中編『風の古道』が大好きなんです。普段歩いている住宅街の道と並行して、人間は立ち入ることのできない古道が通っている。そこにはヒトではないものが往来しており、間違って迷い込んだ青年はそこから脱出しようとする。
どちらの作品もあまり湿度が高い感じではない。暑さ度でいうと40%ぐらい?
[猛暑度=40%]
3.『クライマーズ・ハイ』横山秀夫(平成15=2003年)
夏の光が皮膚に痛いほどだった。(本文より)
この日のことは今でもかすかに覚えてる。
昭和60年8月12日の夜。歌番組に速報のテロップが流れたのが始まりだった。500人以上の乗客を乗せた日航ジャンボ機が行方不明。それから後のニュースは、すべてこの報道一色になった。
自分にとっては、さほど暑かった記憶もない、いつもと同じ夏だった。しかしこの事件の捜索や報道に関わった人々とっては、これほど印象深い夏はなかっただろう。
登場人物たちのセリフの行間から、汗や体温、息遣いまでが漂ってくるかのような作品でした。
[猛暑度=90%]
4.『屍鬼』小野不由美(平成10=1998年)
すでに梅雨が明けたが、部屋の中に浸み入るようにして流れ込んでくる夜気は熱気とは無縁だった。むしろ半袖のシャツに肌寒くさえ感じられる。そもそも渓流に沿って拓けた山村は熱帯夜には縁がない。(本文より)
物語のラストは11月8日だが、事件の発端は7月24日。
長過ぎるという批判もあるが、私はむしろこの長さは必要だったと思う。
当初は夏風邪をこじらせたと思われた村人の変死事件。やがて伝染病を疑われるようになり、事態は徐々に正体を現してくる。このジワジワした過程の積み重ねこそがこの作品の見せ場。
山間の村が舞台なので蒸し暑さはあまり感じないですね。
[猛暑度=50%]
5.『不夜城』馳星周(平成8=1996年)
土曜日の歌舞伎(かぶき)町。クソ暑い夏の終わりを告げる雨がじとじとと降っていた。(本文より)
面白いサスペンスやハードボイルドはそれまでにもあった。しかしこの作品は、主役の男女がそれまでとは違った。利害が一致したときだけ協力し合い、状況が変わればあっさり相手を裏切る。カタギのサラリーマンとはまったく価値観の違う人物をよくぞここまで描いたと思う。それも脇役ではなく主役で。
出だしからして、熱帯夜の湿った空気がまとわりついてきそうな90年代の新宿。不快指数高そうです。
[猛暑度=85%]
6.『姑獲鳥の夏』京極夏彦(平成6=1994年)
梅雨(つゆ)も明けようかという夏の陽射(ひざ)しは、あまり清々(すがすが)しいとはいい難い。坂の途中に樹木など、日除(ひよ)けになる類(たぐい)のものは何ひとつとしてない。ただただ白茶けた油土塀らしきものが延々と続いている。(本文より)
「夏に読みたいミステリ」という企画はいろんな場所で行われているが、選者の年齢に関わらず、誰が選んでも入る鉄板の作品は、今やこれではないだろうか。発表当時はトリックのフェアorアンフェアで議論になったが、ここまで一般に支持されるようになるとは…
発表は平成6年。しかし作中で描かれているのは昭和27年の夏である。そのせいか、朝夕は涼しくて過ごしやすいかつての日本の夏が、理想的なかたちで再現されている気がする。
シリーズの正当な続編は、2006年の『邪魅の雫』以来書かれていないが、もともと登場人物たちは昭和27年の世界に住んでいる過去の住人なので、シリーズを何年放置しても年を取らないのがいいところ。
[猛暑度=55%]
7.『匣の中の失楽』竹本健治(昭和53=1978年)
七月十四日。まだ盛夏には間がある筈なのに、この日は平年の最高気温を八度も突破したという。前日までは、どちらかと言えば平均気温を下まわっていただけに、予想もつかぬ、狂ったような猛暑だった。熱病のような午後。(中略)
舗装中のアスファルトが融け出して、倉野の靴底にいやらしく粘りつく。倉野は先程から、しきりに腕時計を気にしていた。(本文より)
どんどん時代を遡り、ついに昭和の作品へ。
この作品に夏のイメージを持っている人は多いらしい。やはりこの出だしの描写のインパクトが強いのだろう。「舗装中のアスファルトが融け出して」という、昭和の時代とは思えないような猛暑の描写だが、この日を境に気温のピークは過ぎ、翌日には平年以下の気温になったとある。この頃ならそうだろう。真夏日が何日も続くことはまずない。
事件は7月に始まり、終結するのは秋。意外にも長い期間の物語である。
[猛暑度=80%]
8.『悪夢の骨牌』中井英夫(昭和48=1973年)
人間は、夏といえば夏休みという連想から死ぬまで逃れられないらしい。
私も毎年、夏になると子供の頃の夏休みを思い出し… そして現実逃避したくなる(笑)。そんな気分のときに最適の作家が中井英夫だったりする。
この『悪夢の骨牌』は連作短編集というふれこみだが、実際は長編に近い。収録されている短編は、独立して読むと意味不明なものも多く、章立てととらえたほうが分かりやすい。
新年から始まって12月で終わる、1年間の物語だが、それでも夏のイメージが強いのは「戦後」や「闇屋」といったワードが、作中に何度も繰り返し出て来るからだろうか。
戦争が終わって二度目の夏のことで、そのころの東京は、幼児がクレヨンでいたずらに塗りたくったような色彩に溢れていた。(本文より)
[猛暑度=70%]
(以下、後編に続く)。