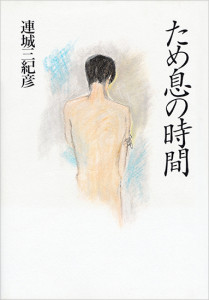数年前連城三紀彦が亡くなったとき、入手困難になる前にと、かき集めた未読作品群。時間ができるたび少しずつ消化しています。
『ため息の時間』
雑誌「すばる」に1990年3月号から1991年2月号まで連載された作品。恋愛小説と思って油断して読み始めたらとんでもない怪作だった。
ストーリー的には、三十一歳の洋画家(=僕)とその恋人の康子、僕がセンセイと呼んでいるイラストレーターの辻井とその妻の洋子、ほぼこの四人だけの物語。さらに僕はセンセイに同性愛的感情を抱いているという複雑な四角関係。
いかにもモデル小説っぽい体裁を取りながら、連載第二回で、僕=連城三紀彦ではないと作者が断言し、さらにラストシーンとして予告されていたエピソードが予定を変えて途中で登場したり、連載終了直前の回には再び作者と関係者らしき人物が登場し、モデル問題について語り合ったり… さらにこの過剰なメタ技法が、何のために導入されたのかさっぱり分からない。
センセイのモデルが脚本家のA氏(おじさん世代には神代辰巳「赫い髪の女」や澤井信一郎「Wの悲劇」の脚本家として有名)であることは定説になっているらしい。確かにこの前年のエッセイ集『一瞬の虹』にそっくりの人物が登場する。しかし本当にこれが暴露小説ならば、これでは分かりやすすぎる。漫画家が編集者やアシスタントをモデルに作りあげたキャラを、長編にも登場させてみましたというノリと変わらない気がするのだが。
「君が言う “センセイ” が誰なのか、たとえば君の一番身近にいる人物や当のセンセイ自身にもわからないような話の進め方を僕がすればいいんでしょう?(略)」(本文より)
もしもこの作者の企みが実現したとしたら、その作品は問題作とも異色作とも呼ばれず、他の作品群に埋もれているはず。まさかこの小説、完全犯罪に終わった他の小説の種明かしのために書かれたものじゃないでしょうね? だからこれは最初から失敗作となる運命だった…
そんな馬鹿げた勘ぐりをしたくなる。
もともと著者のミステリは、高い文章力でまず結界を張り、その中でしか通用しない動機を配置するのがいつものやり方。そこに登場する男女は目的遂行のためなら冷酷なまでに強い。それがこの作品では妙にもろさやある種の切実さを感じるシーンが多く、そういう意味でも心に残った。
「昔のコートにはいつもその前の年の冬の匂いがした」
こんな印象的なフレーズを目にすると自分は安心するのだけど、若い人が読むと古臭い文章に思えるのかなぁ。
『終章からの女』
昭和四十×年の暮れ、荻窪のアパートで一人の男が殺される。重要容疑者としてマークされた妻の斐子(あやこ)は、二十代のころ一瞬だけ付き合いのあった弁護士の彩木を訪れ弁護を依頼するが、なぜか必要以上に重い刑罰を望む…
読み終わった直後、これは短編でやることだろうとつぶやきたくなった。初期短編を思わせる斜め上の展開と超絶動機。それを長編でやってのけるとは。『ため息の時間』のような小説も、ミステリの一種と思えばそう読めなくはないけれど、これは堂々たるミステリ作品。作者の狙いが明確で迷いがない。手元にあるこのミスのバックナンバーを確認してみると、95年版の21位。あと一つ順位が上がって20位以内に入って、もう少し注目されていれば、それ以降の作品に違った展開があったんだろうか。
『ため息の時間』を読んで「違う作品の種明かしのために書かれたのでは?」なんて考えが浮かんだのも、直近でこれを読んでいたからかも。すでに『終章からの女』を読んでいる人には分かってもらえるかもしれない。これはそういう話だ。そしてこの作者は、それをやり遂げる人だ(笑)。
このところ関連写真をひとつ掲載するのが恒例になっているので、今回はこれを。
連城作品買い漁りのころお世話になった神保町&九段下エリア。これは九段下交差点の近くにあった九段下ビル。昭和二年竣工の雑居ビルです。いつ頃まで建っていたのか… 記憶が定かではないけれど、現在は広い空き地のまま数年間そのままになっていますね。